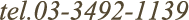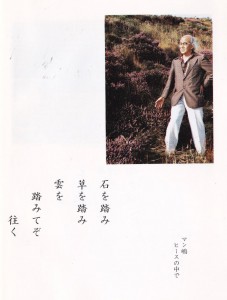2月19日より3月2日までイタリアのミラノのファーフェアーに行ってきました。
ここ2年北欧に行ったので、ゲルマン系の言語を話す人々と、その数年前は東欧のチェコやポーランドなどのスラブ系の言語を話す人々に接することができました。
イタリアはラテン系の言語を話す人々で、おしゃべり、私にはうるさいくらい。
北欧はやや無口で、口数が少ない、という印象を持ちました。
ヨーロッパの街角や門構えにケルト模様などがあるのを見ると、ヨーロッパの古層には「ケルトCelt」がありそうだと見当をつけてきた。
ケルトに詳しい鶴岡真弓さんの書かれたものを眺める程度に読んでいるのだが、
私自身、大学で、シングの戯曲「海に乗りゆく人々」をテキストに、アイルランドのケルト文学を甲斐満里子先生の授業に啓発され、アラン島まで行き、自分のペンネームにまでしてしまった。
被圧されたマイナーな人々にシンパシーを感じ、同情を寄せることから興味が始まった。アイルランド、スコットランド、ウエールズ、コーンウォールなどの島のケルト、 フランスのブリトンなど大陸ケルトが、他のヨーロッパの地域より、色濃く「ケルトの香」を残している。
来年のオリンピックを意識してか、NHKの連続ドラマの宣伝が、
新宿の地下通路に「みつどもえ脚(トリスケル:trisquel)」のポスターが張られていてびっくりした。
マン島(アイルランドとイギリスに挟まれた小さな島)の国旗をもじったものだ。
この島はオートレースで有名だが、ケルトやバイキングに関係した島、しっぽのない猫(manx)も有名。
南側の傾斜地は一面のヒースだった。嵐が丘のヒースクリフ(ヒースの崖)はこんなところで拾われたのかな・・・などと思った。
鉄格子のもう誰も住んでいない庭を覗きながら、リチャード・クレーダーマンの「秘密の庭」を思い出した。ほぼ毎週一度はこの曲を懐かしんで弾く。
この曲でBmを覚えた。Cmより半音低いのだが、Cmよりもう少し、複雑な感傷を出せるようで、気に入っている調。シベリウスはBを「赤ワインのような調だ」と言っている。
最近、ユングの研究家である河合隼夫の「ケルト巡り」から印象にのこった文面がある。『近代ヨーロッパに生まれた人間関係は、個人はみな別々だというところから出発している。別々の人間だから、言葉によってコミュニケーションを図らねばならない、そして、それは可能なのだという信念がある。だから言葉や理論を中心とした人間関係の構築を基本に据えることになる。そして、言語表現をしない人はコミュニケーション能力がないとか、意思を持っていないということになってしまう』
『たとえば、私が花を愛でるときに、私と花の間には魂がある。ところが、私が花を突き放して「いくらで買いますか」などと他人に持ち掛けたら、その途端に魂は消え去ってしまう。その間にあるもの、在間にあるのが魂なのだと考えると、ラフカデオ・ハーンが書いた、柳の精が女になり男と結婚するという話もよくわかるのではないだろうか。柳と自分は関係ないと思っていても、在間を大事にしているとだんだんつながってくるような気がするのだ』
ケルトが文字を持たず、羅連模様や渦巻模様で、人生はどこから始まりどこで終わるのやら、連続模様を好んで使っていることなど、言葉にでききれないものをああいう模様で表そうとしているのでしょう。
 三脚のモチーフは韓国の三色巴や日本の巴柄に繋がるような気がする
三脚のモチーフは韓国の三色巴や日本の巴柄に繋がるような気がする
金谷武洋の「日本語に主語はいらない」という本からも、日本人には、
個人の主体より、まわりの状況でそうする、そうある、というような思考があるらしい。
立つ(自動詞)、立てる(他動詞)と考えがちだが、tate-aruというふうに考えるようだ。
なにかまわりの影響でそうしてある、と言いたげ。英語では人間以外のなにかわからない存在、自然とか、そういう場合、主語に i t を使う。it is fine. it will rain.など
日本人は、アフリカからの長い旅を終え、南から北から、やっとたどり着いたこの島で、縄文の人々が、主語を明確にせず、相手とのできるだけ一体感を保つことで、できるだけ対立感をさける、相手との一体感を醸し出す、ことによって抗争を避けようとした言語文化を私たちは作り上げてきたのでしょうね。
私はとても言語が好きで、いつも英語と日本語を中心に言語のことを考えている。ヨーロッパの系の言語は比較言語学でかなり系統が明確にされてきたが、日本語は複雑でまだまだ十分解明はされていないのが現状。だからなお興味がわく。
私のように毛皮という素材で、デザインにかかわるものにとって、文字以外で、ある種の造形表現をしていることになる。お客様の深層や、素材の持っている深層の表出に、すこしでもお役に立てればと努力をし続けたい。
小泉八雲は、アイルランドの神話や民話にhappy endのものが少ないことと、
日本の「つるの恩返し」などのように、自然と一緒に生きている人間としてとらえているところに共感したのだと思う。
ダウントンアビー公爵一行が、スコットランドのいとこのシュリンピーの領地に避暑に出かける。メイドのアンナがアイリッシュダンスのリールを踊るシーンがある。
円に繋がり、繰り返し回るダンスはケルト模様のようだ。
日々の生活は、まわりのことを思ったり、ふと自分に帰ったり、ケルトの螺旋模様のように繰り返されてゆく。
現在の私たちは、合理性を積み上げた科学技術をみごとに発展させたが、逆にこれによって滅ぼされようとしている。
河合隼夫は「ケルト巡り」のあとがきに、
ケルトの代表的な渦巻き模様の紋様のように、私はまさに「ケルトを巡って」内に入ったり外に出たり、昔々の世界にいるかと思うと、急に現在の真っ只中にいたり。私の感情も思考も巡り巡りして、ふと気が付くと入口にまた立っていた。
天文学者の佐治晴夫さんが「宇宙がただ一点の光から発現したことを思えば、人間がいかに相互依存して生きていかなくてはならないか理解できると思う」
(この位の飛翔力のある思考をしたいものですね。)
「宇宙探査機ボイジャーが太陽系を抜けるとき、振り返って、太陽系を写した写真を思い出して欲しい。宇宙の中の 水色のたった1点の星が私たちだと」と彼は詩情を込めて語った。
星を見ていると、何万年前の光や数秒前の月の光が今到達している。一瞬に宇宙誕生から全ての時の光を見ていることになる」「・・・・ファーストなんて言って欲しくない」と彼は言っている。
わたしの仕事も30年前の過去が、今、目の前にあり、未来に向けてデザインされる渚にいるのだ。
上手く行かなかったこと、失敗したこと、などをケルト風に円として、どこかに連続してゆくように考えたら、また再生に繋がるのだ。
繰り返し複合する円環の中に生きているという示唆に富んだケルトの文様にしばし我が身をゆだねてみよう。